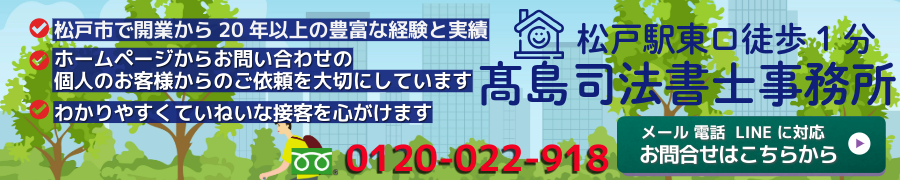遺言書の検認
(最終更新日:2025年9月17日)
遺言書の検認を司法書士にご依頼いただいた場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出も司法書士にお任せいただけます。
また、家庭裁判所への遺言書検認申立にあたっては、多数の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本などを収集する必要がありますが、市区町村への戸籍等の請求手続きについても司法書士が代行できます。
さらに、遺言による不動産の名義変更(相続登記)の手続きも司法書士の専門分野です。したがって、遺言書による遺産相続手続きについては、すべて司法書士に安心してお任せいただけます。
遺言書の検認やその他の遺産相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。当事務所へのご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
遺言書の検認(目次)
1. 遺言書の検認とは
2. 検認の手続きの流れ
2-1.家庭裁判所への申立て
2-2.検認期日
2-3.検認済証明書の交付
3. 必要書類など
1. 遺言書の検認とは
自筆証書遺言など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です(ただし、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除きます)。また、遺言書に封印がある場合には、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと開封しなければなりません。
遺言書は検認を受けなくても効力自体に影響はありません。しかし、相続や遺贈の登記を行う際には、家庭裁判所の検認済証明書が付された遺言書が必要です。さらに、遺言書を隠匿・破棄する行為は相続人の欠格事由ともなりますので、遺言書が見つかった場合には速やかに検認の申立てをすべきです。
ただし注意すべきなのは、検認を受けたからといって、その遺言書が法的に有効と認められたわけではないという点です。「検認は、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確にするものであって、遺言書の実体上の効果を判断するものではない」とされています。
したがって、検認を受けた遺言書があっても、必ずしもその遺言書によって相続登記などの遺産相続手続きを行えるとは限りません。遺言書が法的に有効と認められない場合には、相続人による遺産分割協議が必要となる場合もあります。
自筆証書遺言による遺産相続手続きを行おうとする際には、まずは司法書士にご相談ください。
2. 遺言書検認の手続き
遺言書の検認を司法書士にご依頼いただいた場合、「遺言書検認申立書」の作成だけでなく、家庭裁判所への提出まで一括してお任せいただけます。
また、申立てにあたっては多数の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)などを収集する必要がありますが、市区町村役場への戸籍等の請求手続きも司法書士が代行することが可能です。
2-1.遺言書検認の申立て
遺言書の検認を受けるには、「遺言書検認申立書」およびその他必要書類を準備して、家庭裁判所に申立てを行います。申立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
2-2.遺言書検認期日
申立てからしばらくすると、検認の日を指定する「検認期日通知書」が家庭裁判所から送付されます。通常は、期日を決定する前に家庭裁判所から検認日程についての打ち合わせの電話が入ります。検認期日は、申立てから1か月以上先になることもあるため、早めの申立てが望ましいといえます。
検認期日には遺言書を持参します。封印のある遺言書を開封するには、相続人またはその代理人の立会いが必要とされていますが、申立人以外の相続人全員が必ず出席しなければならないわけではありません。
遺言書の検認では、遺言の方式に関する一切の事実を調査し、その結果を記録した「検認調書」が作成されます。調査内容には、日付・署名・押印の有無や記載内容のほか、用紙の種類や枚数、使用された筆記用具なども含まれます。
2-3.検認済証明書を付した遺言書の交付
検認手続きが完了すると、「検認済証明書」が付された遺言書が交付されます。検認済証明書は遺言書とホチキス等で綴じられ、割印(契印)が押されます。
検認済証明書は裁判所書記官が作成し、例えば「令和7年(家)第1111号 遺言書検認審判事件」といった事件番号が付されます。その文面には「この遺言書は令和7年○月○日に検認されたことを証明する。」といった文言が記載されます。
・遺言書検認済証明書(東京家庭裁判所での例)
3.遺言書検認申立ての必要書類等
家庭裁判所へ遺言書検認の申立てをするには、次のような書類等が必要となります。
遺言書検認申立の必要書類等
- 遺言書検認申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本・住民票除票(または、戸籍の附票)
- 遺言者の住民票除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票(または戸籍の附票)
- 収入印紙 800円分
- 切手 110円×相続人の数×2枚
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ